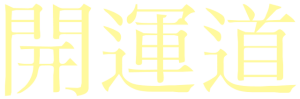流れ行く 大根の葉の 早さかな
高浜虚子
上流で皆が川で大根を洗っている。葉がとれて川に流されている。大根を洗うぐらいなのでとても綺麗な川なのでしょう。そこに緑のみずみずしい葉が一枚流されてきて、それがさっと目に飛び込んでくる。キラキラ光る水の中に鮮やかな緑がさっとすぎる。
そんな様子を私は想像します。貧相ですね(笑)皆さんはもっと想像を膨らましてみてくださいね。
来るものがいない、頼るものがいない。窮地に立った時や何か始める時にはそんな状況になることがありますね。そんな中で一人でやらないといけなくなることもあります。人間の人生のひらきかたは、その状況をどう捉えるか一つで変わってきますね。
一人ぼっちで苦しいと捉えるか、「私はこうする」と腹を決めて周りに流されずに動くのか。気学では「万初」といい、腹を決めろといいます。
周りの評価におそれず、一本の目標で動き続けて成功した例はいっぱい在りますね。私が今思いつくのは、例えばソニーのウォークマン、青色ダイオードなどです。ウォークマンは社内で反対されても創りあげていったものですね。青色ダイオードは誰もが諦めていたことをただ一人で長年やり続けた結果ですね。青色ダイオードによって、今の電子機器はガラッと変わってしまいました。映像機器だけでなく、照明、信号、PC、スマホなど、生活をがらっと変えてしまいました。商品というより産業革命みたいなものですね。
この一人でいくことの清々しさというものが、流れゆく大根の葉のようですね。
「人がどうするかなぁ?」ではなく「私がどうするか」。その目標に向かって「たった独りでやるのぉぉ?」ではなくて「私から全てが初まる。これが全ての初めだ。」とするか。
そうして独りで歩いてきた人の周りに人が多く集まってきて、初めは独りで大根を洗っていたのが、多くの人が洗いにやってきてワイワイやるようになりますね。小さな川だったものが気がついたらとてつもなく大きな川になっていきますね。例えばウォークマンとか青色ダイオードかのように。このなんと清々しくも雄大なことか。
下から上へ気持ちを立ち上げる、自分を立ち上げる。自分がないと周りに流されるだけになります。自分が大根の葉としたら、単に川に流されていくのか、自分で海に向かって行くのか。それによって人生の拓き方がかわってきますね。
気学はこの大事さを教えてくれます。