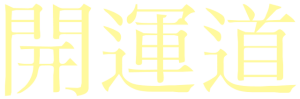指定した年から、数十年分の十干・十二支・九星を計算します。
カテゴリー: 計算
土用の計算
指定された年の、土用開始の日時を計算します。
*計算に誤差はつきものです。節替りの時閒などの値は保證(保証)できません。國立天文臺(国立天文台)、萬年暦を參照してください。誤差と無保證(無保証)を御理解の上、自己責任にてご判斷(ご判断)ください。
本命・月命・最大吉方・同会・傾斜の計算
生年月日から、九星気学で使用する、本命・月命・最大吉方・同會(同会)・傾斜を計算します。ラッキーカラー、ラッキーナンバーも出します。
生年月日を入力してください。
*生まれ日が3〜10日のときは、干支・九星がずれる可能性があります。生まれた時閒が必要です。時閒は母子手帳等で確認できるでしょう。
*それ以外の日に生まれた人は、時閒の指定は00:00:00で問題ありません。
*「記憶する」ボタンで計算結果を記憶すると、こちらの計算ページで、自分の凶方を赤で塗ることができます。
*その日の十干・十二支・九星を知りたいだけ、あるいは、その月の切り替え日時を知りたいだけなら、こちら や こちら で計算できます。
*「最大吉方」は移動方位だけを指すものではありません。多くの利用法があり、村山流と言われるものにとって大事な槪念になります。移動方位だけと考えたり、用語を變更するのは、村山流と立場が違います。
日盤切替の問題
陰遁陽遁のサイクル:
日の十干十二支九星
で、切り替わりの現在のルールを述べました。
しかし!
これはズレます。ズレを放置すると、遠い未来、今の冬至付近の切り替えが、夏至付近の切り替えになることもあります。ざっとやってみると、半年以上前にずれこむ事もおこります。冬至切り替えが立春付近まできて、さらに超えて、ぐるっと一周なんて時もあります。
前述のルールを述べた投稿では、ここまで言及していません。計算を簡単にするために固定して考えています。実は、離れた過去や未来を計算するとズレが大きく出ます。あてにならないのです、本当のことを言えば。
このズレをどうするかは確定していません。未来の人類に丸投げです。
実は、天象学会の『萬年暦』の1905年(明治38)と1915年(大正5)の動きがイレギュラーです。
なぜ調整を入れたのか、なぜこの値に決定したのか、理由不明です。今年で100年。伝承が残っていません。
1905-12-20七赤
1905-12-21七赤
4020日経過 (4200 - 180)
1916-12-22七赤
1916-12-23七赤
どうです?素敵でしょう?全くわからなくて。
A.いつどれぐらいズレるか?
現ルールに基づくと、何がどうしてどれぐらいズレるか、みてみましょう。
解決策を未来に託すためです。私の代では無理でしょう。
A1.前提
前提①: 地球の1太陽年の日数: 365.24219XXXX で、前後する。 前提②: 1年の日数は、整数化せねばならない。年数も同じ。 前提③: グレゴリオ曆の閏日の発生: 400年間で100回未満にする。97回にしている。 ex. 西曆1〜400の時、西曆100年、200年、300年は平年。西曆400年は閏年。 なお、西曆に0年、0世紀はありません。 前提④: 干支は60のサイクル。 前提⑤: 干支九星は180のサイクル。 前提⑥: 通常は「甲子」(60干支の、1番目)で陰遁陽遁を切り替える。 前提⑦: 切りかえを調整する時は「甲午」(60干支の、30番目)で切り替える。
意外に多いですね。
A2.case1.400年間で考える
理解しやすいように、1〜400年の400年間で考えてみます。(400年はグレゴリオ曆の閏の基準期間)
(a).日数 = 400 * 365 + 97 = 146097日(∵閏年97回) (b).8400のサイクルの回数 = int(146097 / 8400) = 17回。 (c).8400のサイクルの合計日数 = 8400*17 = 142800日。 (d).(c)が何年ぶんに相当? = 142800 / 365.2422 ≒ 390.973
(d)の時にぴったり冬至なり夏至なりがきていれば問題ないはず。
整数化して考えると、391年でぴったりならラッキー。
だが現実はズレがあります。
391年でぴったりではない。ぴったりになって欲しい時に、何日ズレているか?をみてみます。
(e).391*365 + (97-3) = 142809日。 ∵391年間 → 潤になる年400年、396年、392年の3回はこない。∴97-3 (f).(e) - (c) = 142809 - 142800 = 9 この時、現実は、グレゴリオ暦が9日多い。 (g). ∴391年で、9日ずれる(前に移動する)
となりました。
391年で9日。結構な誤差です。
では、一ヶ月ズレるのはいつぐらいか、大まかに予想してみましょう。
(h).∴30日ズレるのは、391*3 = 1173年 30日は大事。前提⑦で使用する量、また、一ヶ月も変わると、月の節氣(干支九星)が変わってしまうため
A2.case2.1173年間で考える
case1で、1173年が臭うとわかりました。約30日のズレは大変です。
では、正確に、何日ズレるでしょう?case1と同じ考えでやってみると
1173年間の (i).閏の回数 = 97*2 + 90 = 284 ∵ 1173/400 ≒ 2.9325。400年完全に含む回数は2回。97*2 余りは、1173 - 400*2 = 373年。 この373年間の閏の回数は 90 回。(∵400,496,492...,376無し。4*93=372より自明。その中から、100年、200年、300年を除く) (j).1173年間の日数 = 1173*365 + 284 = 428429日。 (k).428429/8400≒51.003。 ∴ズレ = 428429 - 8400*51 = 29日。
29日でした。
場合によっては30日の可能性もあるでしょう。が、まぁ、29日で考えましょう。
B.どう調整すべきか?
1173年で29日、400年で9日。どう調整しましょう?
ここでやっかいなのは
前提④〜⑦
です。冬至切り替えなら、冬至が出現する節に切り替えたい。しかも甲しばり、子午しばり。
うまいことできるんかいな?という感じです。
丸投げします。
未来の人類、頑張れ〜。
iCalendar形式の十干十二支九星
google calendarにインポートして使用出来ます。.icsファイルです。
ブラウザでgoogleカレンダーを見た場合、十干十二支九星は画像になります。といっても文字を画像にしただけのものです。
ブラウザ以外のgoogleカレンダーと同期できるアプリでは、文字での表示になります。
googleカレンダーにインポートする場合は、新しいカレンダーを作って、それにインポートすると使いやすいです。
日の十干カレンダー
2001年からスタートしています。(Readdleのカレンダーアプリが2001年からしか動かなかったため)
日の十二支カレンダー
2001年からスタートしています。
画像は3通りに色分けしています。文字の場合はカッコで分けています。なぜそうしているかはセミナーでお伝えします。
日の九星カレンダー
googleカレンダーへのインポートに時間がかかるので、10年単位にファイルを分けました。見たい期間だけインポートしてください。
4200日目での切り替えが2020年6月20日にあります。その点を考慮しています。
二十四節気カレンダー
- 2015年〜2019年のカレンダー(2015/07/17追記)
土用カレンダー
- 2015年〜2019年のカレンダー(2015/07/17追記)
年の十干十二支九星
年の十干十二支九星のプログラミング。
西暦y>=1以上とします。
十干 = (y+6)%10
ただし:0=甲, 1=乙,....., 9=癸
十二支 = (y+8)%12
ただし:0=子,1=丑,...., 11=亥
九星 = 9-(y+7)%9
ただし: 1=一白水星,2=二黒土星,....9=九紫火星注意点が一つあります。
九星気学風水では新年のスタートは「立春」です。二十四節気の考えです。正確に言うと、太陽の視黄経が 315°になる”日時”です。天文計算をして出す必要があります。
立春はほぼ2/4ですが、何年かに一度、2/3になったり2/5になったりします。
例えば立春が”2/4 07:00″だとしますと、”2/4 00:00″だと”前年”で、”2/4 08:00″だと年があけています。